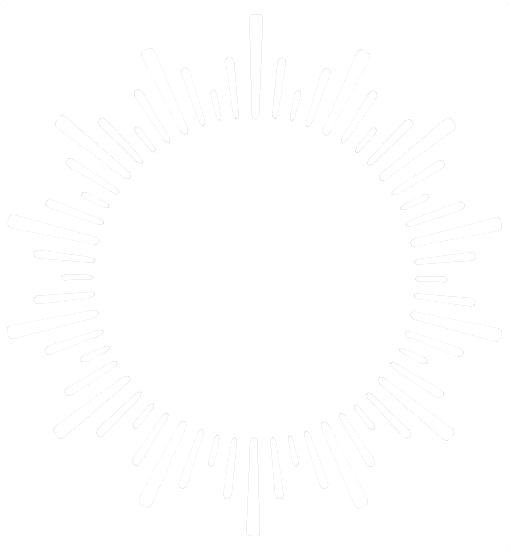訳分からんタイトルと分厚さに二度見必死の「クロコダイル路地」がすごいぞ
クロコダイル路地…この、どんな物語なのか全く想像できないキャッチーなタイトルと、それから分厚い、分厚すぎるボリューム感(物理)が本作の存在を格別のものにしていると思う。
解説で「皆川博子版『二都物語』」という表現が出てきたけれど、その比喩が一番しっくり来るなあ(本当の二都物語は未読のくせに知った口をきく)。
フランス革命前後の22年間を民衆の立場から描く大河ドラマ的作品…、と聞くと敷居が高いというか、何それ面白いの?と身構える人もいらっしゃるかと思うけど、中身は思ったよりも読みやすくて面白いので軽率に読んでみたらいいと思います。
最終的にはこの分厚さもむしろご褒美というか、「いやもっと分厚くても…いいよ!」という境地に至る(至った)ので安心しよう。
ざっくりあらすじと感想
始まりはフランス革命前夜、1788年10月の“竪琴の全音階を奏でるような”秋のこと。
本作の主人公というか語り手は何人か居て、それぞれの立場から、その時の出来事が語られ、紡がれ、総体を形づくっていくという形式で進みます。
ところで、何人かの視点をつないでいく語り口って、皆川作品によく見られる手法ですよね。「U」もそうだし、「倒立する塔の殺人」も、「死の泉」にも同じような書きぶりでしたね。
文字を追うわたしの両目が、ページを、世界を通り越して、語り手の目線に宿り、秋の古城を見つめる。ページをめくるわたしの両手はいつしか語り手の堅い手のひらに宿り、震えながら冷たい銃を握る。
何人もの語り手の、それぞれの体験を、泳ぐように渡る楽しさ。読み手たるわたしだけが、語り手たち当人の知らない他の事情を知っているという全能感。
一人称の小説ってやっぱり好きだな、と思わされます。それも全て、著者の筆力の成せる技なのですが。発想力と写実力が凄すぎて、皆川さんはタイムトラベラーなのだなと、読むたびに確信を深めています。
さて、主な語り手は、以下の立場の人たちです。それぞれが「フランス革命」ー歴史上最も大規模と言われた市民革命ーに、己の運命を狂わされていくことに。
まずはロレンス。フランスのナントで生まれ育った所謂ブルジョワ。初登場時は13歳。母はフランス貴族の家系で、父方はイングランド貴族…が亡命によりフランスに渡り、今では奴隷貿易等々で財を成しているが、フランスにおいては平民扱いであるため、貴族階級をお金で買おうと画策している。
1788年の10月、ロレンスは母方の親類であるフランソワ15歳(母は貴族家系なので、フランソワも当然貴族)およびフランソワの従者であるピエール17〜18歳とともに、秘密の古城を散策する…という、キッズなら誰でも胸を踊らせるひと時の冒険を体験する。
二人目の語り手はジャン=マリ。彼はナントに住む貧困層で、初登場時は14歳。籠作り職人の父と蝋燭作りの内職をする母、母の作った蝋燭を売り歩く10歳の妹コレットという家族を持つ。日雇いの力仕事に従事し、生活に余裕は全く無い
そんないつも通りの1789年7月18日(同年7月14日にパリのバスティーユ牢獄が襲撃され、フランス革命が勃発する)が描かれるところから、彼の物語は始まる。
決して交わることは無いはずだった富裕層と貧困層…ロレンスとジャン=マリが、パリで勃発した革命の波がナントまで届いた騒乱の中で出会ったことにより、運命は加速していく…。
この後、語り手は貴族フランソワの従者ピエールになったり、ジャン=マリと生き別れになってしまった妹コレットになったり、また新たな登場人物を交えたりしなが進み、物語は層を増していくのです。
予備知識が合った方が絶対面白い
フランス革命…ギロチンで王妃マリー・アントワネットが殺されたことくらいの知識しか持ち合わせていない(世界史受験だったのに笑)わたしでも十分楽しめたものの、やはり素養があった方が絶対より一層楽しめる訳で。
およそ230年前(日本で言うと江戸時代、寛政の改革が行われた頃)、王政を廃止し資本主義の発展を志した民衆による革命が実際に起こったのだよね。
そう聞くと大義ある正しい行いのように思えるけど、実際には罪無き人々が大勢断頭台に立ち、殺しきれないため溺死刑まで編み出され、富は再配分されるのではなく一部の人間たちで再度独占され、それがまた新たな戦いを生んでいった。
なんとも、なんともまあ血なまぐさいこと。
王様たちの優雅な暮らしぶりやマリー・アントワネットというキャラクターの強さばかりに気を取られていたけれど、フランス革命が本当はどんなものだったのか、について、本作を通して知ることになりました。大義は確かにあったのだろうけど、早々に失われてしまったのだろうな。
本作はフィクションに違いないけれど、フランス革命に関する記述はきっと限りなく事実に近づけてあるのだろう。その史実の狭間に、ロレンスやジャン=マリが潜り込んでいるのだろう。そんな風に素直に信じてしまいます。
だって、まるで見てきたように庶民の日常が、泥地での乱戦が語られるんだもの。ロンドンの悪臭すら漂ってきそうな文章、というか。
そんな緻密で濃密な描写が1000ページ以上も弛むことなく続くんだから、改めて作者の力量に慄くばかり。すごいな皆川さんはほんとに…
皆川作品には常に、大きな歴史のうねりの中で、もがきながらも抗いきれず呑まれていく諦念が描かれているように思う。死者と狂者が見せる美しい悪夢を一緒に体験しているような。
幻想的で、蠱惑的でもあり、時にはひどく残虐で無慈悲で、どうにも惹きつけられる。
読みながら、「美しい破滅」という言葉が頭に浮かんでいました。
そっちに行っては駄目なのに、行くべきではないのに、登場人物たちは、破滅へと引き摺られていってしまう。
タイトルの意味とは?
クロコダイル路地…この不思議なタイトルは、革命という大きなうねりの中では一人一人の人生などあっけなく歪まされていく…その数奇な運命の交差点、という意味が込められているのかなあ?と思いました。
クロコダイルという繰り返し登場するモチーフ。
この存在をどう解釈するか、読んだ人の感想を色々と聞いてみたいけど、わたしは「心の奥底にある自分自身」ってことなのかなァ〜と思ったのです。
誰もが押し込めた本能や隠したい裏の顔を持っている。ロレンスにとって、ピエールにとって、それが鰐の形だったのかなって。
巻末の解説の方の意見にも頷くところが多かったです。(書評家の方なのですね。さすが、分かりやすい解説だった!)
そして、不意に現れるバートンズたち!
“彼ら”が登場するなんて全然知らずに読んだので、現れた瞬間、誰かに向かって叫びたくなった。(ねえ、バートンズが出てるよ!!!!!!!!って笑)
※バートンズは、個人的に一番好きな皆川作品「開かせていただき光栄です」「アルモニカ・ディアボリカ」に登場するキャラクターたちです。作品の感想はこちらから!
ここまで感想を書いて、改めてすごい作品だなあと思ったので、より丁寧に味わうべく、史実と照らし合わせながら物語を振り返ってみることにしました。
※大いにネタバレしているので、未読の方はまずお読みになってからどうぞ!
ネタはバレバレ!クロコダイル路地で学ぶフランス革命
(サンキューWikipedia先生!)
絶対君主制の下で、第一身分(聖職者)は14万人、第二身分(貴族)は40万人、第三身分(平民)は2,600万人いて、第一身分と第二身分には年金支給と免税が特権として与えられていたのですって。
財政危機に陥ったフランス王朝は、1789年5月5日に「全国三部会」を開催して、国王と第一から第三身分までみんな交えて議論しましょうぜ、という会を開いたのですって(いつまでこの口調続くんだろう)。
ここで、在りし日のロレンスはフランソワらと共に、三部会の前日にヴェルサイユで行われた聖体行列を見物していたのだったね。※文庫版P47参照
国王以下が大名行列的に練り歩くイベントのようだけれど、この時は群衆は国王陛下万歳!と叫ぶ一方、王妃に対しては罵声を投げかける者も居たとか。
盛装した母の結い上げた髪より数倍も高く、王妃の結いあげた髪は天に向かってそびえ、全身を飾った宝石が煌めいて、王妃は光の中にあるようだった。
P48〜49
王妃マリー・アントワネットの華美な装いが描かれている。この時はまだ、破滅の匂いはロレンスやまだ幼いフランソワの鼻まで届いてこない。そこかしこを漂っていたに違いないけれど。
その後、1789年7月19日、農民や貧民をブルジョワが率い、ナント市内が襲撃される。この時ジャン=マリは10歳の妹コレットと生き別れ、ロレンスは馬車が襲われそうになるがアルノーに助けられ母の元に帰り着く。
「アンドリュー氏は、ナント城の司令官ゴヨン氏と、ひそかに話をつけてあるのです。ゴヨン司令官は、立場上、一応開城を拒否しますが、市の安全確保の名目で、アンドリュー氏の提案を入れ、彼らを入場させるはずです。
P100
ナントにおける騒乱を先導しているアンドリューについては、ググってもよく分からなかったけれど、皆川先生のことだから丁寧な取材に基づく史実なのだろうなあ。
コレットを轢いたかもしれない馬車がロレンスの乗っていたものであることが判明し、ジャン=マリは助祭のエルヴェと共にロレンス宅を訪れる。ここでエルヴェはロレンスの母の甥(妾腹)であることが明かされる。う、うーん?ややこしい…
8月上旬、国会では封建制廃止が布告され、8月下旬には<人間および市民の権利宣言>が公告されたとの記載がP140辺りに出てくる。
Wikipediaによればバスティーユ牢獄襲撃の動きを経て成されたものだが、国王が主権者であり、国王がこれらの布告を承認しなかった、と書いてある。
物語の中でも、「<我がラ・レリ家は、断固、ヴェルサイユにあって国王陛下をお護りする。封建制廃止だの、人権宣言だの、馬鹿げた法令は、陛下は無視しておられる。陛下が批准されない限り、法令は無効だ>(P142)」という手紙がロレンス宅に届く。
しかしこの後、事態は更に深刻になっていく。
十月に入ってから届いた報せは、祖父を青ざめさせた。母はまたも失神した。 <国王陛下とご家族が、暴徒どもによってヴェルサイユ宮殿からパリのテュイルリー宮殿に強引に移らされた。穏やかな行幸ではない。民兵団と武装した市民数万がーそれも女どもが先立ちになってーヴェルサイユ宮殿内に乱入し、陛下とご家族を拉致同然に連れ出したのだ。>
P142
これもWikipediaに載ってましたね。“パリの数千の女性たちが武器を持って雨の中パリ市役所前の広場にあつまり、ヴェルサイユ宮殿に乱入…”とのこと。なんで女性だったんだろ?
ここにも、それだけで本が一冊書けそうなドラマがあるなあ。
この後、作中では色々な法令が批准され、ドニ神父の運命が少しずつねじ曲がっていくのだけれど、それはWikipediaには載っていなかったな。
どうしても王政に対する記述がメインになってしまうのだけど、次のイベントはこの場面。
軟禁状態であったテュイルリー宮殿を、ご家族共々、ついに脱出された。しかし、行程はもたつき、身柄を確保せよという革命政府の布令が先に行き渡っており、ご一行はヴァレンヌで拘束され、パリに連れ戻された。
P168
俗に言う「ヴァレンヌ事件」が起こったのだね。この辺はベルサイユのばらの方が(史実通りか知らないけども)詳しく書いてあるかもね。
ナントは変わらないだろうとロレンスの父はコメントしたけれど、国王への反感は徐々に広がっていく。
P170あたりに、奴隷貿易で利を得ていた商館に大きなダメージを与える植民地での奴隷による叛乱、そしてその背景にイギリスが絡んでいることが語られる。この辺りから、国家間の思惑や駆け引きも交わってきて、複雑さが増してくるのだよね。むつかしい…
その後、フランソワの従者ピエールがロレンス宅を訪れ、ラ・レリ伯一家はコブレンツ(今はドイツの都市)に亡命し、フランソワは亡命貴族が集まる反革命軍に参加する旨が語られる。※P175あたり
ここで、本作通じて繰り返し登場するラテン語のフレーズが登場するんですよね。
quo fata trahunt, retrahuntque, sequamur.
(運命が運び、連れ戻すところに、われわれは従おう)
『アエネーイス』というラテン文学の最高傑作と言われる叙事詩からの引用なのだとか。
ここから物語は1792年4月に革命政府がオーストリアに対して宣戦布告し勃発したフランス革命戦争、そしてフランソワ属する反革命軍の動きに焦点が当たっていく。
ウィキによれば、フランス革命政府vsオーストリアという構図なのだけど、オーストリアの軍に亡命貴族たち反革命軍が参加していて、連合軍となってパリまで向かい、王様を解放しようとしていたみたい。
フランソワはヴァレンヌに向かい長官を逮捕するが、この時には既に“8月10日事件”(国王と王妃が滞在していたテュイルリー宮殿に民衆が押し入り、国王一家をタンプル塔に幽閉した事件)が発生しており、守るべき国王が幽閉状態であることが知らされる。
この何とも言えない時間差…!通信が発達した今だったら起こり得ないことだけれど、独特の無常さがあるよね。
パリをめざし進軍していた反革命軍は、途中で停戦協定が結ばれたため、既に攻め落としていたロンウィまで戻り、体制を整えることに。
1792年10月19日にロンウィへ帰着。その頃には、9月21日に王政廃止とフランス第一共和政樹立を宣言していたのだった。
そうして我々は知らされた。パリの議会ー国民公会と呼ばれるーはすでに、王政廃止、共和制を宣言していたのだ。フランス王国は消滅し、フランス共和国と国名が変わっていた。
P194
一方ロレンス側では祖父・父・母がかつての使用人らに囚われ、自身は執事ドーファンに助けられるが、その後裏切りにあい、ブーヴェの手に落ちることになる。革命については、以下のように語られている。
この年ー一七九三年ーの一月、国王陛下が処刑されるという、あり得ないことが現実に生じたのだ。<革命>は狂乱状態だ。
P203
あらゆるフランス革命を取り扱う物語で最大の出来事であるルイ16世の処刑が、あっさりとモノローグで語られるところに、本作の独自性が出ているよね。
解説にもあったけど、「地方における革命」が本作でのテーマだったのだろう。溢れる史実や資料の中から取捨選択をして、物語に史実を織り込んでいくのは、とても大変な作業だっただろうなあ。
ジャン=マリの視点で、ロレンスの祖父・父・母がギロチンの犠牲になる場面が描かれる。こわい。それと、ここでコレットがナントにおける勢力者であるギデオン・ミルズの元にいることが判明する。
ピエール側では、後に“ヴァンデの反乱”と称される戦いに身を投じることになり、フランソワの学友だったアンリが活躍することになる。
物語の中で、王党派の指揮官だったカトリノー、デルベらの名前も語られる。ウィキにもこの人たちは載ってるね。
フランソワはナント攻撃軍に参加することになり、ここでジャン=マリ、ロレンス、フランソワ(+ピエール)がナントで交錯することになるんだなあ!
丁寧に物語を追っていくと、改めてストーリーの重厚さに感心させられるわ。
折々に反革命軍の非道さや戦いの中での犠牲についても触れられていて、痛ましい気持ちになる。
語られない死や痛みは、目を覆いたくなる程溢れかえっていたのだろうな、ということが容易に察せられる。
共和軍(あお)も王党軍(しろ)も、プロイセン軍と変わらぬ蛮行を重ねるのを、フランソワは目にしている。カトリノー、デルベなど指揮官らは掠奪虐殺を禁じているけれど、末端までは指令はゆきわたらず、青が虐殺に走れば、白は報復と称して輪をかけた蛮行に及ぶ。(中略)食糧は、村々から強制的に調達する以外に、補給のすべがない。青も白も、奪うのだ。
P241
こんな描写たちが、読み手にある種の諦念や無常を植え付けていく。
ロレンツはブーヴェに匿われイギリスへの亡命の機会を待ち、ジャン=マリはフランソワたちが攻め込んでくるのに対抗する防衛軍に従事することになる。
素人集団なのですったもんだした結果(ここの描写がユーモラスでちょっと救いになったよね)同じ親方の下で働いていた赤鼻トマが撃った銃撃が、王党軍の指揮官カトリノーに当たってしまう。
ジャン=マリは気が重くなった。ドニ神父様を幽閉した奴らの勝利か?抗いようのない大きな力が、躰のまわりで渦を巻いている。濁流の中の木っ端みたいだ……俺は。
P283
フランソワ側は、共和軍がねじろにしていたロレンス宅を捜索しており、ダヴィドとココを発見する。うああすごい近いところにロレンスが!
この時彼がまろび出てきたら、また運命は変わっていたのだろうな。
ロレンスは共和軍に囚われていたことを恥じて、隠れてフランソワたちをやり過ごすことになる。そしてフランソワたち王党軍は、(赤鼻トマの銃弾によって負傷した)カトリノー負傷の一報を聞き、ナントから撤退を余儀なくされる。
この後フランソワ達王党軍は、共和軍の熾烈な攻撃に苦しめられるが、イギリスへ亡命した貴族らに助けを求め、使者としてエルヴェが王党軍を訪れる。英国からの救援物資と援軍を求め、援軍の上陸地点を確保するため英仏海峡をめざすことになる。
(この夜に語られる、フランソワとピエールの交流が沁みるんだよなあ、ある意味ピエールの人格や人生を決定づけたんだものね。他人にとっての些細なやり取りが、当人にとって重大なことって、よくある話だよね)
ジャン=マリはというと、国家総動員令により再び共和軍に身を置き戦うことになり、ここで赤鼻トマを失う。
ジャン=マリ自身は偶々中隊長を庇った形で負傷し、名誉の負傷という形で除隊する。
再び視点がピエールに切り替わった時、悲劇が彼らを襲う。
援軍と合流すべく戦っていたが敗戦し、アンリとフランソワは敗走せず三万の軍勢に四百という手数で挑み大敗。
ピエールはフランソワを見失い、捕虜として投獄され、そこでドニ神父と出会う!いや〜この伊坂幸太郎もびっくりな繋がりね。
ドニ神父様がとことん敬虔で善良で、逆に悲しくなってくるのよね。死亡フラグがね、もうビンビンすぎて…
この後、ピエールとフランソワは捕虜として船に押し込まれ、ジャン=マリは捕虜を移送する船の細工を命じられ、ロレンスは渡英するための船を共和軍に押収され…
ここで運命が再び交錯し、ロレンス・ジャン=マリ・ピエールの三人は結果としてブーヴェやエルヴェと共にイギリスに渡ることになる。
この辺りについて、ウィキペディア上ではさらっと一言、“捕虜になった者はナントに連行され、ロワール川に浮かぶ廃船に積み込まれて沈められた。”と書かれている。本当に溺死刑は存在していたのだな…と、暗い気持ちになった。
こうしてフランス革命の中で起こった“ヴァンデの反乱”は鎮圧され、物語は舞台をイギリスに移していくのでした…。
ロンドン編に移る第4章はP517からスタート、それに対して本作の総ページ数はP1014なので、ここまででちょうど半分くらい。いやあ、長い!笑
ウィキペディアと本作を交互に見ながらここまで纏めるのに、うーん三時間くらいかかったわ。笑
本編はここから史実とはちょっと離れていく訳だけれど、フランス革命の方はというと、共和制を敷いた後に新たな権力者(作中にも名前が何度か登場するロベスピエールさんね)が独裁を行い、その揺り戻しでロベスピエールさんが逮捕・処刑され、再び不安定な戦況となった後に、かの有名なナポレオンが登場。
クーデターを起こし、1799年に新たな政権(フランス第一帝政)が起こったものの、ナポレオン失脚後は再び王政復古の時代が来たのだとか。
一体どのくらいの人が革命によって命を散らしたのだろう。
戦争を題材にした作品に触れるといつも同じことを考える。
命の価値、命の重さは不変でもないし平等でもない。
王政を打ち倒し資本主義の勃興へと至ったフランス革命は、圧政に苦しむ民衆にとっては正道だったのかもしれないし、圧政を正す指導者がいれば、あるいは革命のやり方が違っていれば、もっと血を流さずとも済んだのかもしれない。
革命は起こすべきだったのか、そうではなかったのか、わたしたちはこの出来事から何を学ぶか…。何故革命が起こったのか、という背景は多く書かれているけど、革命そのものに対する評価は見つけられなくて、もう少し深掘りしてみたいなと思った。
おまけ:物語に登場する有名人物
アンリ・ド・ラ・ロシュジャクラン:ファミリーネームめっちゃ発音しづらいね。若くして反乱軍の中心人物になったからか、ウィキでも手厚く紹介されているね。
ウィリアム・ウィルバーフォース:P172にちらっと登場。奴隷廃止主義者。
プリンセス・ランバル:P199にちらっと登場。マリー・アントワネット付の官長だったが虐殺されたとのこと。ベルばらにも出てくるのかな〜と思って調べたけど未登場とのこと。いい人そうだった。
ジョセフ・フーシェ:P204あたりから登場。フーシェの名で何度か触れられる。態度を変えて時の勢力者とうまく付き合ってたから、「カメレオン」ってあだ名がついてたんだって。
ジャン=バティスト・カリエ :P208あたりから登場。溺死刑を生み出した人として史実上も有名なのだとか。
あれっ意外とこのくらいだったかも。
書き出してみて気づいたけど、ウィキに載るほどの有名人は大体名前だけの登場なんだな。(最も頻出したアンリですら、軍議でフランソワに意見を求める台詞くらいしか無かったもんね)
彼らの名前を引用しながら、オリジナルの人物たちがイキイキと活躍する。そうすることで、史実や実在人物に関する文献とかと、齟齬が発生しないよう配慮しているのかな。
実はアンリはそんな奴じゃない!みたいな批判は起こりえないものね。
いや〜長かったな今回の記事も。面白さ・熱量と文字数が正比例してしまう癖をもうちょっと何とかしたい。(この文章までたどり着いた方が果たしているのか…?)
最後まで読んでいただき、というかこんなところまでお越しいただき有難うございました。という気持ちでいっぱいです。有難うございました。