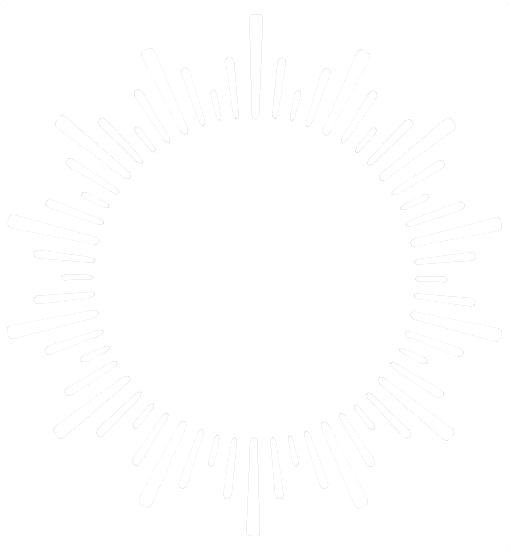初めての「限りなく透明に近いブルー」のお味
村上龍さんの代表作「限りなく透明に近いブルー」を読みました。
「コインロッカーベイビーズ」「半島を出よ」など、気になる作品の多い、読んでみたい作家さんの一人でしたが、暴力的・性的な表現が多いとか、分かりにくいとか、取っつきにくい印象もあり……。けれど、本作はページ数が少なかった(文庫で本編159ページ)ので、「あらこれならわたしでも読めそうと」思い挑戦してみたのでした。
タイトルの響きが綺麗で、印象的ですよね。群像新人文学賞、芥川賞受賞作品です。

主人公のリュウ、彼の恋人のリリー、友人のレイ子・オキナワ・ケイ・ヨシヤマ・モコ・カズオ。米軍基地の街で織りなされる若者たちの青春グラフィティ(ただし全員漏れ無くヤク中)、というあらすじでしょうか。
そう、本作、出てくる人たち全員がしっかり薬物中毒なのです。ぶっ飛んでるなぁ。この飛び具合が文学的に評価されたということなのかな。
さて、「タイトルは知ってるけど中身どんな感じなんだろう?」と思われる方も多いと思うので、ざっくりあらすじとふんわり感想をまず書かせていただき、後半はネタバレ感想と、それらを踏まえた本作の評価を、わたしなりに考えてみようと思います。
ざっくりあらすじと箇条書き感想
本作が刊行されたのは1976年(昭和51年)、村上龍さんは1952年生まれだそうですから、24歳の時の作品なのですね。若い!
先ほども書いた通り、主人公とその恋人&友人たちのデタラメな日常が延々と綴られているので、あらすじも何も…という感じではあります。もともとページ数も短いですしね。
そして、書き添えなければならないのは暴力的・性的・差別的表現が盛り沢山ということ。開始3ページでモルヒネ打った打たないみたいな話が出てきます。
読んでいて気分が悪くなる可能性もあるので、苦手な方はご注意くださいね。(わたしは夜ご飯食べながら読んでたら、ちょうどアレなシーンに差し掛かり、気持ち悪くなって読むのをやめました笑)
ドラックと暴力、日夜繰り広げられる”パーティー”……退廃的でデタラメな日常が続き、その先にあるものは破滅か、それとも?
という作品です。
読むとこんな気持ちになれます。未読の方はぜひ読んでいただいて、共感していただきたい…
- 福生、魔境すぎんか…?
- 顳顬=こめかみ
- 友だちたちの見分けがつかなくて序盤苦戦する
- リュウとリリー、レイ子とオキナワ、ケイとヨシヤマが付き合ってる。これを頭に入れとくと楽かも
- 主人公のリュウはイケメン風なのだけど、私小説風だとしたら村上龍さんなわけで、ご尊顔がちらついて集中しきれない
- リュウは”観察者”の立ち位置なのかと思ったら、いきなり長話するわ女装するわで読み手の身が持たない
- でもリュウみたいな、何考えてるか分からないのに突然はっちゃける人っているよね
もし会話の中で「この本どうだった?」と聞かれたら、「いやぁ〜エグめでしたね、あと福生の治安やばいですね😖」と答えると思います。
ネタバレと本作の評価
あらすじというほどの大きな流れはなくて、薬物の影響なのか、各シーンがぶつ切りというか…突然描写が始まって、突然終わって、また次のシーンが突然始まる…の繰り返しで、全体の大きな流れがあるのか無いのか、それも良く分からなかったです。
お酒をたくさん飲んでしまった時、ぼんやりと、お店での会話や帰路の記憶がまだら状になることがある(そして、もっとお酒が進むと、シャッターが閉まったようにぷっつりと記憶が途切れる…☺)けど、それに似てるのかなぁ。
黒人(という言い方って正しいのかな、アフリカ系アメリカ人かな)たち…オスカー、ボブ、サブロー、ダーハム、ジャクソン…とのパーティーというか、まぁ乱交は、シンプルに痛そうで気持ち悪くて怖いなぁという感想しか出てこなかったです。
中毒者たちのグロテスクな“パーティー”、リュウとリリーの深夜のドライブ、ヨシヤマの激しいDVと自殺未遂、日比谷公会堂でのフェス、無銭入場を殴って止めた警備員への厳しいリンチ、ラリっている間に焼死した15歳の少女、錯乱して鳥に怯えるリュウ…
感想を書くにあたって再度本作を読み返したりもしたのですが、これらそれぞれの断章とも言うべき記述を通して、著者は何を語りたかったのか。いやぁ分からなかった…笑
ただ、当時24歳だった村上龍さんは(そして恐らく10代のリュウは)、きっとすごく怒っていて、こんなひどい話もあるんだぞとぶつけたくて、こんな若者が本当にいるんだぞと訴えたかったのだろう、そんなエネルギーを随所から感じました。
表現は文学的で、語りは終始抑制されているためか、暴力・性描写がたっぷりなわりに読み心地は静かというかフラットな印象で、大げさに言えばピアノの旋律のようだったのも印象的でした。
(解説の綿矢りささんが引用されていた「ジャマイカの原住民が好む血と油で煮つめたスープ」なんて、確かに面白い表現だと思う)
若者の鬱屈、それが静かな語りで表現されること……それらが出版当時、“若者のリアル”だと評価されたということなのかな。
だとすれば…その時代の一部分を切り取って、暴力的な表現も使ってまざまざと見せつけたことが本書の評価ポイントだとすれば…2020年代に読んでもピンとこないのは仕方のないことなのかも。
賞味期限切れと受け取るか、普遍的なものと受け取るか、それが本作の評価が分かれる理由なのかなぁと思いました。
しかし、全体に抑揚がないのはまぁ良いとして、ラストはどういうことだったんだろうか…
蛾を殺した後、腐ったローストチキンを食べて急速に調子が悪くなるリュウ。リリーの介抱も虚しく、鳥に襲われるという幻覚に取り憑かれて七転八倒する。
虫を殺す描写が数回挟まれていたけど、鳥に襲われる、食べられるという脅迫観念は、殺す立場から殺される立場になることの恐れなのかな?
そして、自ら割ったグラスの破片を腕に突き刺すことでリュウは正気を取り戻し、夜明けに病院(なんで病院?腕をぶっ刺したから?あるいは薬物中毒で?)から自分の家に帰って行くところで物語は終わります。
これまでずっと、いつだって、僕はこの白っぽい起伏に包まれていたのだ。
P157より
血を縁に残したガラスの破片は夜明けの空気に染まりながら透明に近い。
限りなく透明に近いブルーだ。僕は立ち上がり、自分のアパートに向かって歩きながら、このガラスみたいになりたいと思った。そして自分でこのなだらかな白い起伏を映してみたいと思った。僕自身に映った優しい起伏を他の人々にも見せたいと思った。
ここが、タイトル回収の場面ですね。この時の「白っぽい起伏」は、リリーと二人で飛行場に迷い込み、離陸する飛行機のジェットエンジンに吹き飛ばされてた時(いや、そもそもこれで合ってる?何でそんなことになったの?誰か教えて…)に出くわした雷鳴だと思われます。
自分がガラスとなり、白い起伏をガラス(=自分)に映すことで、他の人に起伏を見せたい…というのはつまり、リュウ自身が何らかの表現者となることの暗示なのでしょうね。だからこの本を書いたのだというメッセージ。
メッセージは受け取ったけれど、白い起伏・優しい起伏が何なのかはまるで分からなかったよ、とリュウに伝えてあげたい気持ちになりました。もっと分かりやすく書いてくれ😷
本作が私小説だ、これは実話らしい、エッセイのようだ、という口コミをアマゾンレビューなどでも見かけましたが、本当なのかな?
あとがきにて、本作はリュウが書いたものだということが明かされたけど、それはそういう形態の書き方なだけじゃなくて…?カンブリア宮殿などで知識人ぶりをアピールしている村上龍さんは、(元)ヤク中で汚部屋住まいで女装して乱交してたの…?(困惑)
※ウィキペディアにも、「福生での体験を基に…」と記載がありますね。
詩的な表現や過去に前例の無い文章表現などを多用し、当時の文芸界に衝撃を与えた作品である。荒廃していく若い男女を描いたために、よく石原慎太郎の『太陽の季節』と対比される。ストーリーは村上龍が20代の頃過ごした福生市での体験を基にしている。
ウィキペディアより
↑の続きに原題が載ってるのだけど、ヤバくて笑ってしまった。この題名を芥川賞に選んだ人たちの懐の深さがすごい。
面白い!とは決して思わなかったけれど、こういう作品もあるんだなぁというお勉強としては良かったです。村上龍さんの文章や、言葉の選び方や表現の仕方は嫌いじゃないので、そのうちまた別の作品も読んでみようかなぁ。