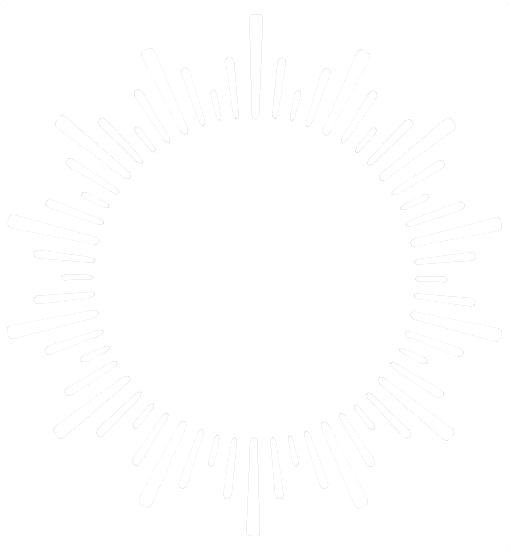原民喜初心者が「夏の花・心願の国」を読んだ
羊と鋼の森を読んで、原民喜に興味を持った人も多いと思う(わたしも、もちろんその一人)。それほど、彼の人の引用された文章は印象的だったから。
「明るく静かに澄んで懐かしい文体、少しは甘えているようでありながら、きびしく深いものを湛えている文体、夢のように美しいが現実のようにたしかな文体」
文体の話なのだけれど、わたしは「こんな人になりたい」と思ったのでした。文体を人に置き換えたら、あら何て魅力的なのだろう。
そんな美しい文章を紡ぐ原民喜さんの代表作「夏の花・心願の国」を読んでみました。
患う妻との生活(『美しき死の岸に』の作品群)、疎開先の広島での被曝体験、直後のヒロシマの様子(『夏の花』三部作)、そして東京に戻ってからの生活・遺作(『心願の国』等)が収録されています。うーん、初心者向き!
果たしてどうだったか
冒頭の「苦しく美しい夏」を読んだ第一印象は、
「これはまるで、神経が丸出しの人みたい」だったもの。
風が吹いても痛むような。(痛風かな?)
こんなに繊細だと、生きにくいだろうなあ、と。
その代わり、何の変哲もない毎日の風景すら、この人の目には美しく、異様に見えるのではないかな、と思った。
それが彼にとって幸せなのか、不幸なのか、よく分からないけれど。
生きにくかったから、自殺してしまったのかなあ、とか。
病に伏せる奥さまとの静かな日常を描いた序盤の作品群は、原さんの私小説めいていて、彼の生涯を予備知識として持っていないと分かりにくい部分も多々あるものの、文章は瑞々しく、静謐で、美しかった。
彼がどれだけ奥さまを大切に思っていたか、それがよくよく伝わってきて。
だからこそ、奥さまが息を引き取ったときの悲しみ、絶望もダイレクトに伝わってきて、胸が締め付けられるようだった。
わたしにもお付き合いをしている人がいて、そのうち結婚するのかもしれないけど、もしわたしが先に死んでしまったら、彼はとても悲しむだろうな、と自分に置き換えて悲しくなったりもした。
子どもがいたらね。忘れ形見、とはよく言ったものだよね。
もし子どもがいたら、それが生きがいにもなって、偲ぶよすがにもなって、救われる部分もあるのではないのかな。
二人きりの生活で、どちらかが先に死んでしまったら、喪失感に溺れてしまいそう。そんなことを思った。
彼は妻の枕頭に坐ったまま、いつまでも凝(じっ)としていた。時間は過ぎて行き、庭の方に朝の陽が射してきた。あたりの家々からも物音や人声がして、その日も外界はいつもと変りない姿であった。昏睡のままうめき声をつづけている妻に「死」が通過しているのだろうか。いつかは、妻とそのことについてお互に話しあえそうな気もした。
P71より
中盤、「夏の花」から連なる作品群は、戦争や空襲が日常になっている異様な平凡が「この世界の片隅に」に通じるものがあるな、と思った。
(実際には「この世界の〜」が本作に通じている、というのが正しいのだけれど)
前半の兄弟のいざこざは正直よく分からん…と思ってしまったけれど、被爆直後の、まさに地獄としか言いようのない光景も、酸鼻をきわめるはずなのに、何故か印象としては静かで、無声映画を見ているような感覚だった。
それはきっと、原さんの文章が、被曝数ヶ月後に描いたとは思えないほど、整然としているからなのだと思った。
世界が地獄に変わってしまっても、生き残った人々はひたすら、1日を生きていく、その繰り返しなのだと思ったし、電車が意外とすぐに走り始めていて、現代より余程全てに時間がかかるだろうに、人間のしぶとさ、みたいなものに胸を打たれたりもした。
ただ、癒えようもない悲しみが、尽きることのない痛みが、あらゆる場所に満ち満ちているな、と。ただただ、悲しい。ただただ、痛ましい。
次に広島に行ったら、この気持ちを忘れずに、せめて花を手向けたいと思った。
最後の作品群、これは残念ながらわたしの読解力ではよく分からなかった笑
フラッシュバックのように原さんに去来する原爆のイメージに、彼自身も混乱しているようだし、目眩を伴うような文章を読むと、こちらの頭もクラクラしてくる。
引き摺り込まれそうな、潮に足を取られそうになるような、そんな力を感じた。
幻想小説に近いのかな、皆川博子さんの小説でも、同じように感じることがあるから。
あの頃、お前は病床で訪れてくる「春」の予感にうちふるえていたのにちがいない。死の近づいて来たお前には、すべてが透視され、天の灝気はすぐ身近にあったのではないか。あの頃お前が病床で夢みていたものは何なのだろうか。
P286,287より
僕は今しきりに夢みる、真昼の麦畑から飛びたって、青く焦げる大空に舞いのぼる雲雀の姿を……。(あれは死んだお前だろうか、それとも僕のイメージだろうか)雲雀は高く高く一直線に全速力で無限に高く高く進んでいく。そして今はもう昇ってゆくのでも墜ちてゆくのでもない。ただ生命の燃焼がパッと光を放ち、既に生物の限界を脱して、雲雀は一つの流星となっているのだ。(あれは僕ではない。だが、僕の心願の姿にちがいない。一つの生涯がみごとに燃焼し、すべての刹那が美しく充実していたなら……。)
遺作「心願の国」の最後。
やっぱりこの作品も、主題が何なのか?何を描きたかったのか?わたしには分からなかった。
ただ、夢と現を彷徨いながら、心に浮かんだ取り留めもない事柄を書きつけたような、美しく、透明で、そのまま消えて行ってしまいそうな…そんな危うさが漂っていた。
何より大切だった奥さまを亡くして、その時から原さんはずっと亡霊でしかなかったのかもしれない、と思った。
だからこそ、自身が被曝しても、故郷が地獄へ変わってしまっても、いつもどこか客観的でいられたのかもしれない。
美しく儚い、やっぱりとっても繊細な人だったんだろうな、と、第一印象通りだなと思った。
夏に読みたい、一度は読みたい作品だと思います。
大丈夫、よく分からないところは飛ばせばいいと思えば、怖くないよ!笑