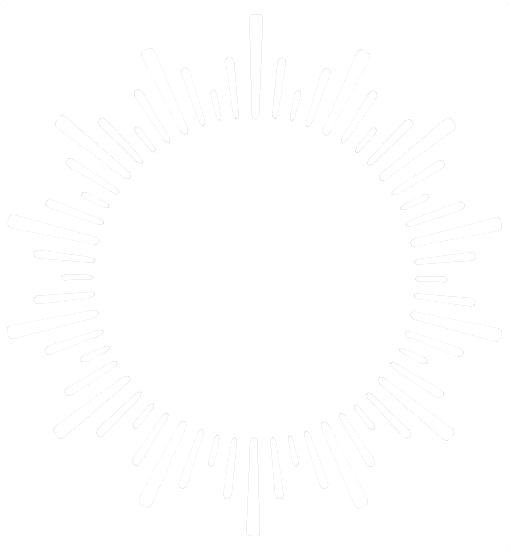本編のその後と隙間を埋める短編と…荻原規子「RDG 氷の靴 ガラスの靴」がやっぱり良かった
ざっくりあらすじと感想

2012年の完結から数年、ファン待望のスピンオフが出ました。
アニメ化も果たした人気の高いシリーズ作品です。
熊野の山奥に神主の孫として穏やかに暮らしていた主人公・泉水子が特殊な力に目覚め、同じく異能を持った少年少女が秘密裏に集まる鳳凰高校に進学することになる…という、恋あり冒険あり不思議あり、和風ファンタジーの新潮流!
と書くと、安易で地味で、あんまり面白そうに感じられない(失礼)のですが、さすがの荻原師匠、抜群に面白いのですわ…
とにかく文章の読み心地がいい。
泉水子ちゃんはとても臆病で内気な女の子なので、終始もじもじうだうだしててちょっとうっとおしい(失礼)感じなのに、ふと気づけば彼女の成長を応援し、驚かされる自分がいて、物語の中にぬるっと自然に入り込んでいる、その文章の妙。
父親から「泉水子の下僕になれ」というトンデモな命令を受ける相良深行くんも、素晴らしいぶっきらボーイ(ぶっきらぼうな男の子を指す造語、わたしの大好物)っぷり。
寝転がりながら読むと、枕をたたいてじたばたしたくなる、甘酸っぱいときめきよ…!
ファンタジーとむずキュンの完璧な融合です。(ソムリエみたいに言う)
スピンオフだけだとさすがに何が何だか分かりませんし、思いっきり本編の後日譚も書かれているので気になる方は1巻から通読しましょう。面白いよ。
以下、読み終えた直後に書きなぐったエモーショナルな感想が続きます。
荻原規子さんは境界に新たな橋を架けた
また会えた、という愛おしさで胸がいっぱいになる。
大げさに言ってしまえば、わたしにとっての荻原作品は、見失ったものを思い出させてくれる縁(よすが)なのだと思う。
この喜びこそがわたしの”核”なんだと。
日常のあれこれに揺らぎ、軸を忘れてしまったとしても、本を開くたびに、またこの気持ちを取り戻し、いつでもここに舞い戻ってこられるのだと気づいた。
勾玉三部作が至高すぎて…という思いはどうしてもあるけれど、RDGは、今を生きるわたしたちのための、現世と常世を結ぶ新しいやり方を試みた物語なんだと気づいたら、途端に大好きになった。
そうか、これは荻原さんからの贈り物なんだなって。
今と昔、それから未来は確かな連なりを持ったものなのだということ。
そして、自分自身が変わりたいと強く願うことが何よりも大切なのだということ。
泉水子の成長を見ながら改めて気付かされた。
その自覚が無ければ他人が何を働きかけたとしても無意味で、逆にそれさえあれば、なんだってできるんだということ。
荻原さんにやさしく諭されたような気がした。
泉水子ちゃんや深行くん、三つ子たちが今では愛おしいし、(初めて読んだ時から、わたしの年齢が進んだことが大きいかもしれないけど笑)それぞれが抱えるもの、その強さと弱さが心に沁みてくる。
残念ながら”世界遺産”という設定にはいまいち入り込めなくて、あと終わり方も微妙だった気がしていて、初読時は「まあ、こんなもんかな・・・?」という印象だったけど、でももう一度、一気読みしたらまた見え方が変わるのかもしれないなぁ。
印象に残った場面たち
影絵芝居
(おれに、紫子さんの手紙を……)
不思議なほど気持ちが軽くなっていた。
ほんの一瞬、泉水子に、小さなお下げの子の面影をかいま見る。いっしょに遊びたいと言って、深行の後を追ってきた女の子だ。口に出す気はないが、深行はちゃんと思い出していた。相手に「憶えていません」と言われてむっとしたので、自分も憶えていないと言っただけだ。
折った便せんを開き、文面に目を通す。とうとう泉水子が歩み寄りを見せたことで、深行がどれだけほっとしているか、顔に出してはなるものかと思っていた。(P26〜27)
九月の転校生
(つい、言っちまったからな……先に鳳城学園へ行って、過ごしやすいこつを見つけてやるって)
昇降口に入る前に、秋雲のかかる高い空をまぶしくふり仰ぐ。
遠い紀伊半島の山奥で、泉水子も、季節の空を見上げただろうか。
深行は孤独が怖くない。人間集団も怖くない。どんな団体に加わろうと、それなりの活路を見つけ出す自信がある。自分のめんどうは自分で見る代わり、他人事に深く立ち入るおせっかいなまねがきらいだ。
そんな深行が、こうして他人のためを考えていることは、自覚しておかしくなるものだった。
おかしいのに、たしかに確実に、自分のはげみになっている。(P57)
相楽くんは忙しい
いつ見てもこの娘は、今にもけつまずきそうな調子でぱたぱた走る。神楽舞を舞うときの崇高さをいったいどこへ置いてくるのやら、すぐに転ぶ幼い子どもを見るようで、そんなに走るなと注意したくなる。
(結局、おれが忙しくしているのは何のためだ。クラスからはずされそうになってまで、忙殺されて走り回っているのは、どのへんにおれの利益があるからなんだ?)(P67)
書き出して見たら、深行の独白ばっかりだな!
おま…お前、泉水子ちゃんのこと既に好きじゃーん!じゃーん…じゃーん……(やまびこ)
本編中に、泉水子→深行への心理描写はあったけど、逆はほとんどなかったと思うので一層新鮮だった。
氷の靴ガラスの靴
「おれって、あんま将来のことを考えられないだろ。だからこの時期になると、どうしても真響がへこむ。それで、鈴原さんのことにも気を回しすぎるんだ。休み中のことを何も言ってくれないと思ってるんだよ」
「えっ、わたし……何もってことはないよ」
言い返した泉水子だが、いくぶんほおが赤らんだ。
「ただ、よくわからなかっただけで。どうするのが一番いいのか……」
「おれには言わなくていいよ。これも、真響の機嫌をなおしたいだけだから」
重要じゃないとばかりに、真夏は笑みを浮かべた。
「あいつには、鈴原さんが打ち明けてくれるかどうかが大事なんだよ。真響はカリカリするとめんどうなことをしでかすから、その前にかまってやってよ」(P97〜98)
泉水子ちゃんと深行の進展具合にやきもきして隠し撮りまで企てる真響の動揺っぷりがおかしいし、それを察した真夏が泉水子ちゃんと話して、あっさり泉水子ちゃんが納得して真響と話をする場面が可愛くて好き。
隠し撮りに駆り出された先輩は、すごい肩透かしだったなって笑
笑ってくださいね!と狙って書かれた文章って逆に笑えなくて苦手です。
なので、ことさらユーモラスに描かれず、こちらが気づいておかしみを覚える、こういうやり方がとても好きだなぁ。
「体に問題がなくても、運命に問題があるの。今のままでは」
泉水子は、何度も考えてきたことだとわかる、驚くほど冷静な口ぶりで続けた。
「中三のとき、わたしに憑依した姫神が予言したの。あと十五年で決まるって。それは、今のわたしに歴史を変えられなかったら、寿命の最後はそこまでということだと思う。姫神が見てきた世界では、いつもそこで死んだの」
真響は息をのんだ。
よみがえる記憶は、六歳の真澄の突然死だった。喪失から生まれる耐えられないほどの大きな心の穴。底知れない絶望の黒。そして、さらに巨大な穴を予想できる、未来の真夏の心停止ーー真響たちが長年抱えた死の予感を、泉水子もまた抱えているのだ。
「それ……もう相楽は知ってるの?」
泉水子はこっくりうなずいた。
「知っている。わかっていて約束してくれたの」
泉水子にとって、約束がそこまで大事だという意味がやっとわかった。深行は、真響が思った以上の深淵を乗り越えていったのだ。泉水子の孤独が、どんなに深いものだったかも理解でき、この柔らかな少女を抱きしめたくなった。そのへんはためらいのない真響であり、衝動のままに抱きしめた。
「だいじょうぶだよ、泉水子ちゃんをぜったい死なせない。私たちがいるからには、必ず守ってみせるよ」
(中略)
「何だか、今、わかった気がしたよ。私たちにはどうして神霊が見えるのか。泉水子ちゃんも相楽も、私も真夏も、どうして真澄と自然にしゃべることができるのか。もしかしたら、私たち、意識しなくても身近に死があるからかもしれない。私は宗田家に生まれたのに、どうしてこの資質が自分にあるのか不思議だったけど」
泉水子はしばらく答えなかったが、少ししてささやくように言った。
「死ぬのは怖い。わたしも怖いの。考えはじめるとたまらなく怖くなる。だから、真夏くんの気持ちがわかると思えるの。でも、真響さんだって同じにすごく怖いよね……相楽くんもきっと。ごめんね」
「謝っちゃだめ、それじゃ卑怯。運命共同体なんだから、私たち」
「……ありがとう」
「感謝もだめ、対等じゃないのはだめだよ。私たち、チームになるんでしょう」
真響が言うと、泉水子は真響の肩に顔をうずめた。
「そうだよね。もう少しこうしていていい?」
そこはかとなく、相楽深行に一勝したという気分のする真響だった。(P133〜135)
荻原さんって体言止めすることが少ないなと思ったので、
「喪失から生まれる耐えられないほどの大きな心の穴。底知れない絶望の黒」が特に印象に残った。
真響の中で、本当に本当に大きな、飲みこめないほどの塊だったんだなって。
泉水子の孤独や恐怖、それでも押しつぶされずに立ち続ける強さがよく伝わる、まさに名場面。
「真響は目立つし、大勢にちやほやされて見えるけど、仲のいい友だちは今までできなかったんだよ。それはおれも同じで、おれたちに真澄がいたせいだ。おれの心臓の問題もあるし、真響の究極の望みってのもある。ぜんぶを明かしてつきあえる友人がいるとは、とうてい思えなかった。鈴原さんが現れてからだよ、きょうだい以外の他人でも、隠し立てしなくていい人がいると知ったのは」(P175)
真夏って本当にいい子だな…
無邪気でやんちゃだけど、とても大人な一面もあって。
しっかり者の真響を裏から支えてるんだよなあ。
落ち着いて考えてみれば、克己がどれほど口で三つ子を引き受けると言おうとも、真澄の存在を真に理解できるはずがない。いとしさと恐ろしさが交錯する神霊に出会った感触を、現実社会しか知らない彼が味わうはずがないのだ。今もこの先も。(P196)
“いとしさと恐ろしさが交錯する”という一文がやたら響いた。
言葉のチョイスが好き。
どんな感覚なんだろう…と想像して、なんとなく理解できそうな気がして、でも絶対に「こんな感じだ!」という確信には至れない遠さ。
だからこそ響くのかなあ。
「このわしに、非を認めろと言うのか」
真響も顔を上げた。こぼれた涙をぬぐわずに口を開く。
「わかって、おじいちゃん。克己くんには防げないことが実際に起こったの。この領域の知識を、私たちはまだまだ深めていないの。そして、この領域でもっとも強大な力を持っているのは、今のところ鈴原泉水子さん。鈴原さんはとてもいい子だから、私は真澄のきょうだいとして、真夏といっしょに力になってあげたい。そのためにこそ、三人で生まれてきた気がするの」
宗田重蔵に、うなずく気配はなかった。前々から頑固な性格なのであり、簡単に納得してくれないことくらい、真響も承知していた。それでも、今日初めて知り得たこともある。真夏が心停止したと見えたとき、忍びの作法をかなぐり捨てて救助に走る祖父だったことだ。ふだんは態度に見せなくとも、実はそれだけ真夏を思いやっていたのだ。
重蔵は黙ったまま立ち上がったが、去り際にもう一つ意外なことを言った。
「カブトムシの約束は、わしも十年来忘れたことがなかった。今度の夏には見せてやろう」
祖父が通路の先に消えてしまってから、真夏が肩をすくめて言った。
「じいちゃんには、やっぱり六歳の真澄なのかなあ。今なら、戸隠のどこにいるカブトムシだろうと真澄には知れたことなのに」
「でも、けっこううれしいじゃん。じいちゃんがどのカブトムシを言うのか、今から楽しみだよ」
真澄はにこにこ顔でそう答えていた。(P248〜249)
泣く…!(泣いた)