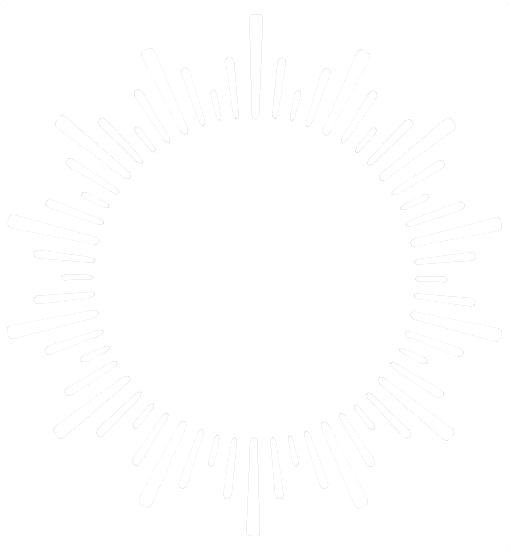吉川英治文学賞受賞「死の泉」は、繊細さと狂気が織りなす美しき地獄絵図だった
2025年春、著者の皆川博子さんが旭日中綬章を受賞されましたね〜!おめでとうございます!
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000940.000012754.html
わたしが皆川さんに出会ったのは比較的最近(といいつつ、10年くらい経っている気はする)で、ファンとしては新参者ではありますが、大好きな作家さんの一人で、他の皆川博子作品もいくつか感想を書いているので、よかったらタグ「皆川博子」から見てみてください😌
当記事では、皆川博子さんの代表作として有名な「死の泉」のあらすじ紹介&ネタバレ感想をお届けします!
あらすじとざっくり感想
皆川博子中級編とも言うべき力作!
(ちなみに個人的初級編は「開かせていただき光栄です」です)
第二次大戦末期、ナチの施設〈レーベンスボルン〉の産院に端を発し、戦後の復讐劇へと発展する絢爛たる物語。去勢歌手、古城に眠る名画、人体実験など、さまざまな題材が織りなす美と悪と愛の黙示録。1997年の「週刊文春ミステリー・ベスト10」の第1位。第32回吉川英治文学賞受賞の奇跡の大作!
黙示録って、「隠されていた事柄を明らかにしたもの」という意味だそう。
確かに本作を形容するのに、黙示録とは良く言ったものだなあ。
第二次世界大戦下のドイツ、ナチ親衛隊が「優秀な血統を増やすため」設立した収容所、レーベンスボルン。
父親のいない胎児を抱えたマルグレーテは、好奇と偏見の目に晒されると理解しつつ、苦渋の選択としてレーベンスボルンで働きながら出産することを選ぶ。
そこで目にする収容所の実態とは…?
”優れたアーリア人”であったために祖国から攫われた幼子たち、
あまりに早熟すぎた美少女、
人為的に二つの体を一つに結合された蛙、
老いた血に若い血を、我が血は汝が血、
…それらが意味するものとは?
本作は、作中にも登場する”とある人物が執筆した小説を翻訳した”というテイなのですが、本当にその時代のその場所に居た人物が描いたような、真に迫る文章に圧倒されっぱなしでした。
皆川作品は押し並べて「皆川先生、この時代生きてた……?」と思わされることが多いのですが、本作まさにそれ。皆川先生レーベンスボルンに居たん?
何故そのような体裁を採ったのかもきちんと伏線回収されるので、もう最初から最後まで皆川先生が掛けた魔法に惑わされているような……なんていうか、掌で踊らされている感がすごかった笑
マルグレーテの養子、エーリヒとフランツ、そしてマルグレーテの実子であるミヒャエル。
三人の子どもたちが進まざるを得ない道、辿らざるを得なかった歩みを思うと、ただただ胸が痛んだ。
あくまでも本作はフィクションではあるけれど、第二次世界大戦、ナチの収容所で、一体何がどこまで行われていたのだろう。人に底知れぬ狂気に、飲み込まれてしまいそうな読後感でした。
以降、ネタバレ全開で「印象に残った場面」とわたしの解釈が続きます。
未読の方はご注意ください!
ネタバレ感想:印象に残った場面
寄せ集め家族の仮初めの平穏
クラウスと結婚し、フランツとエーリヒを養子とし、実子のミヒャエルと穏やかに閉じ込められたように、戦火の中で平和に暮らすマルガレーテ。
一方、各地の収容所が閉鎖となった関係で、シュタインヘリングのレーベンスボルンは各地から押し寄せる乳幼児の受け入れでオーバーフローしており、異臭と阿鼻叫喚の様相を呈していた。
そんな中で、自分たちのすぐ近くに、清く平和に暮らしている親子がいる……妻は自分たちのかつての同僚であった……、という事実は、収容所で働く彼女たちにどれだけの嫉妬を巻き起こさせただろう。
それが易々と想像できてしまうだけに、この平和は遠からず絶対崩壊するじゃん!という不安と緊張感がすごかった。
マルガレーテ宅に漂う、美しいクラシックと破滅の足音、その対比に目眩がしそうだった。
マルガレーテの夢想
戦争のために記憶と思考を飛ばしてしまったマルガレーテ、年齢は…ギュンターがミヒャエルから手記を預かり読み解く場面、混乱と混同を繰り返す彼女の思考が流れ込んでくるようで、悪夢を文字に起こしたらこのようになるのだと思わせる筆致に乗り物酔いしたような感覚になった。すごい。
レナとアリツェの行方
なんとおぞましい…投薬によって体の成長を無理やり早め、成熟したために子どもを産ませようとしたものの、やはり体が耐え切れず死んでしまったレナ、彼女は12歳だったと言う。
そして、レナは貴重な成功例であったがために、彼女を長らえさせるべく、双子の妹であるアリツェは体を繋がれてしまった。
そして、身体を結合されたままミイラ化した二人の少女。
頭の中で勝手に像を結ぼうとして、嫌悪感がそれをシャットアウトさせた。
細部まで思い描くことなんて、到底できない。おぞましすぎる。
生の冒涜、生命の軽視、糾弾する言葉はいくらでも湧いてくるけど、でもこれに近しいことが、きっと実際に行われていたのだろう。
科学者たちは自分の研究を追求することに夢中で、そのための”材料”はいくらでもあって…。
わたしたちはもっと知るべきなんだろうな。ふと気づくと、闇の底からレナとアリツェがこちらを見つめているような気がした。
フランツの決意、インゲの愛
真実を知ってからもう一度読み返したくなる場面。
そりゃそうだよね、当時10歳程度だった彼の決断を、どうして責められよう。
フランツが苦しまなかった訳がない。仮初めの暮らしが彼に何も与えなかった訳じゃない。だって、フランツは顕微鏡を欲していた!(涙)
「神様なんて……。インゲ、誤解しないでほしい。おれは、自分を責めはしても、したことを悔いてはいない」
「罰あたり」
平手打ちの音がつづいた。そして、「神様が与えてくださった最後の機会だよ」インゲの声にやさしみがこもった。
フランツのすすり泣きは号泣に近くなった。そのあいまに、「ナイン」フランツは言った。「ナイン」
「ベッドに行って、おやすみ、悪魔の子。おまえのためにわたしができるのは、祈ることだけだ」
その後のインゲの言葉は、低くて聞き取れなかったが、声音はいっそうやさしかった。
「悪魔の子」と言いながら声音がいっそうやさしいって、何それ…!泣く。
最初読んだ時、(責めはしても後悔はしてないって、その二つは一緒じゃないの?)と思ったけど、最後まで読むと、その二つが違うことがよく分かった。
フランツの罪は幼いミヒャエルを奪い、自分の過失でミヒャエルの男性器を損なってしまったこと、そしてエーリヒとして育てたこと…。
自分を責めるのは、ミヒャエルを守れなかったことに対して。
フランツはミヒャエルが辛い思いをするたびに自分を鞭打っていた。
けれど後悔していないというのは、ミヒャエルを奪ったこと、そしてエーリヒとして育てたこと、だったんだな。なるほど…。
常にエーリヒのよき兄であろうとしたフランツ。マルガレーテに信頼と愛情を寄せ、置き去りにされたフランツ。クラウスに愛される声を持っていないと自覚しながら、医師になる夢を与えられたフランツ。
ミヒャエルの足を傷つけてしまったとき自らの腿にナイフを突き立て、クラウスに帝国の男と褒められたことをいつまでも覚えているフランツ…。
フランツは、クラウスを憎み切ることが出来なかったのかもしれない。
けれど、エーリヒに憎しみを植え付けることをやめられなかった。
それほど、彼の負った傷は深く、癒されることが無かったというこのなのだろう。
彼の賢さと純真が、フランツとエーリヒにとって恐ろしい運命を招いてしまったのだな。
切なくて、やりきれなくて、でも甘美さも漂わせる…。すごいや皆川先生(脱帽)。
地底湖での告白
次々と疑問や謎が暴かれていき否応無く盛り上がるこの場面、映画「オペラ座の怪人」をイメージしながら読みました。
地底湖、美に捕らわれた狂人、狂人に魅入られた美女、美女と愛し合う優男……。イイネ……。
違うのは、ファントムはクリスティーヌを愛したが故に彼女を生かしたけれど、ヴィッセルマンはマルガレーテの美しさのみに執着したから、彼女を残そうとしたこと。
前者からは美しい悲劇を、後者からはただおぞましさと醜さを感じた。
いやほんと、ヴェッセルマンはやばい。
彼の中で論理は一貫していて、でもそれがどうしようもなく社会通念とかけ離れている。
これがいわゆる、サイコパスってやつなんだな。
便利な言葉なだけに簡単に使われがちだけど、簡単に済ませられないほど、ヴィッセルマンは、異質で極端だ。
ラストシーン、二人のミヒャエルはギュンターと共に避難し、フランツはクラウスと心中することを選ぶ。
そこに、マルガレーテが残った…?
そして、レナとアリツェ、テオの関係性は…?
ここは正直、何度読み返してもよく分からんでした😂解説があったら読みたいな。
あとがき
あとがきと言いながら皆川さんの最後の仕掛けが展開する、構成の妙!
【超ネタバレ注意:あらすじ箇条書き】
訳者である野上晶は原作者であるギュンター宅を訪ねる。ギュンターは作中の人物像とは異なり背が低く贅肉のたるんだ中年男性であった。
著者自身が作中に登場するのは「嘘を本当らしく見せかける手段」、マルガレーテは実在し存命であると語る。
また、実在した人物のその後だと言いながら、カウンター・テナーとなったミヒャエルが歌うレコードを野上に聞かせる。
「私が造ったミヒャエルは、ソプラノの音域まで達する」
そう言いながら席を立ったギュンター。
野上はギュンター不在の間、赤い革の背表紙のノートを発見する。マルガレーテの手記と思われるそれは、原作の内容とは異なり、
「…フランツはわたしの側に駆け寄った。パンツァがおどりかかり、彼の喉笛を噛み切った。そのとき以来…」
で手記は途切れる。
このときフランツと読んだのは、ギュンターであろうと野上は考える。だとすれば、今自分が会っているギュンターは誰なのか…?
そのとき、席を外していた原作者が戻ってくる。手記を手に震える野上を見て、原作者は「爆発するような笑い声」をあげる。
原作者の脇から見えた隣室の様子を野上は目撃する。
そこには、
「淫らにあおざめた女が、けだるくソファに凭れ、うつろは目を宙にあずけていた」。
その女は、ミヒャエルの歌にあわせくちびるを動かす。そして、ひざ掛けの下からのぞく彼女の足とならんで、「細い弱々しい足が二本、ゆれていた」。
いやいやいやいや、こわい!
爆発するような笑い声、「私が造った」という発言、そして彼の容姿から想像するに、原作者はクラウスで、彼の元にはマルガレーテがいたということでしょう。
細い弱々しい足が二本、は、マルガレーテに誰かの体をくっつけた、ということ?レコードのミヒャエルの他に、カストラートにされてしまったミヒャエルがいる?
(ギュンターの子のミヒャエルは既にカストラートだけれど、クラウスが求める歌声ではなかったし、「私が造った」という発言に馴染まない。クラウスの子のミヒャエルが、その後カストラートにされたということかな?だとしたら、レコードで歌声を響かせていたミヒャエルは誰?レコードのミヒャエルはクラウス実子ミヒャエルのその後で、マルガレーテとクラウスの間にその後第二子が生まれていて、それがカストラートになった、とか…?)
でも、パンツァ(第二章で登場した犬)に噛み殺されたのは本当にギュンターなのかな?それってマルガレーテの手記の中の話だもんね?
そして、仮にギュンターは犬に噛み殺されてしまったとして、フランツは、エーリヒはどうなったのか?クラウスに殺されてしまった?
ああもう、分からん!分からんが、すごい!ってなる。笑
堅く踏みしめていた地面が実は湿地だったような、信じていた世界が崩れ去ってしまったような感覚が、服部まゆみ作品と共通するものだよなあ。
最後までお読みいただき、有難うございました!
このブログでは、星1つ〜5つまで個人的評価別にカテゴリ分けされているのと、「ファンタジー」「偏愛」など、キーワード別にタグ付けしてあるので、是非気になる本を探してみてください。
カテゴリ別に本を選ぶ
★★★★★:押し付けてでも読んだ方がいいと思うレベル
★★★★:問われたら面白かったよ!と元気よく答えるレベル
★★★:もし興味があれば読んでみたらいいと思うレベル
★★:むしろ面白かったと感じる人の意見を聞きたいレベル
特集記事を見る
薔薇のマリア:ライトノベルの皮をかぶったハードノベル、最高
空色勾玉:数多の少女たちを沼に落としたであろう古代ファンタジーの北極星
白鳥異伝:世界の果てに離れた幼馴染を求める古代ファンタジー、話が重い
図書館の魔女:突如現れたファンタジーの新星にして超大作、ロマンの塊
風が強く吹いている:箱根駅伝に臨んだ10人の挑戦、悲しくない涙が止まらない
ほたるの群れ:未完ですが大層面白い現代のファンタジー、胸が痛い
どうか、あなたの本選びの参考になりますように!